エフェクターは、簡単にエレキギターの音を変えてくれる効果的なアイテムですが、使い方や周囲の状況、メンテナンスによってはノイズの温床となってしまいます。
ここでは、それらのノイズの種類を分析し、原因を究明して、しっかりとした対策について考えていきたいと思います。
エフェクターのガリノイズ
ガリノイズの原因
エフェクターのコントローラー(ボリュームなど)を回すとガリガリとノイズが乗ったり、音が出なくなったり、ジャック部分を触ると発生するガリガリ、バリバリという大きなノイズを『ガリノイズ』と言います。
『ガリノイズ』が発生する原因は、部品の劣化や摩耗によるものです。
又、ポット類を動かさないで放置しておくと、接点に埃や錆が溜まって発生する場合もあります。
エフェクターのガリノイズ対策は接点の掃除で解消
軽いエフェクターのガリノイズ場合は、ボリュームポットやジャックの接点を、接点洗浄剤や金属磨きで掃除すれば直ります。
しかし、掃除が困難な回路の場合は、部品交換が必要になるかもしれません。
こうなると、故障ですから自分で何とかできる問題ではなく、修理に出したほうが安全です。
ブーンという低いエフェクターノイズ
ブーンという低いエフェクターノイズの原因
エフェクターに低い音でブーンというノイズが乗ることがあります。
これは、電源(ACアダプター、パワーサプライ)から混入するノイズである場合が多いです。
なぜエフェクターの電源からブーンというエフェクターノイズが混入してしまうのでしょうか。
ACアダプターには、トランスという部品が使われています。
トランスは、コイルを2つ向い合せた構造で電圧を下げる(100Vを9Vに下げる)ための部品。
コイルに電気を流すと当然磁力が発生するので、周囲に電磁波を放出します。
しかし電磁波がギター信号に混入するとブーンというエフェクターノイズになるのです。
又、最近のACアダプターは『スイッチング方式』というものも増えてきています。
スイッチングACアダプターは、トランス式よりも小型、軽量で、熱も持たないのが最大のメリットですが、その反面スイッチングノイズが発生しやすいという欠点があります。
ブーンという低いエフェクターノイズ対策は電源交換
まず、ACアダプターやパワーサプライを交換してみましょう。
それでも直らなかったらエフェクターボード内の配置を変えてみるのも有効な解決方法です。
又、パワーサプライを止めて乾電池に替えると解決することがあります。
電源交換で解決したら、改めて電源回りを一新して見るのはいかがでしょうか。
ブーンという低いエフェクターノイズ対策のまとめ
- ACアダプターやパワーサプライの交換
- エフェクターボード内の配置を変えてみる
- パワーサプライを止めて乾電池に替える
ジーというエフェクターノイズ
アース不良が原因
ジーというエフェクターノイズは、主にエレキギターの弦から手を離すと酷くなる種類のノイズです。
アース不良が原因のノイズは、エフェクターを配線しているシールドコードからノイズが乗っている可能性が大きいです。
全てのエフェクターをバイパスにしてもジーというノイズが消えない場合は、絶対にシールドコードが原因です。
アース環境の改善で対策可能
まず、シールドコードをチェックしましょう。
パッチケーブルなど、楽器店でオマケにもらったものは、すべて交換しましょう。
エフェクターの数が増えるほど、シールドコードには細心の注意を払わなければいけません。
周期的に繰り返されるエフェクターノイズ
スマホや携帯端末が原因
「ジートットット・・・」というエフェクターノイズが繰り返されている状態です。
最近は話題になることが少なくなりましたが、ガラケーの時代から携帯端末は電磁波が出ていると言われていました。
その当時は、電磁波は有害で人体に影響を及ぼすなどと言われていましたが、近年は、そのような心配はないことが判明したので、いつの間にか立ち消えた話です。
とは言っても、電磁波が音響機器や精密機器に影響を及ぼすことは明らか。
周期的に繰り返されるエフェクターノイズはスマホや携帯端末が原因なのです。
スマホを機内モードに切り替える
スマホにチューナーアプリをインストールして使っている人もいると思います。
又、エフェクターやアンプの設定を、メモ代わりに写メっている人もいるでしょう。
そういう人は、機内モードにして電波をオフにしておけば、スマホの電磁波ノイズは解決できます。
なお、スマホの電源を切る必要はありません。
スマホについている「機内モード」は、まさに電磁波対策の機能なのです。
ちなみに通常の状態で、スマホが着信すると、バリバリバリという、もっと凄いノイズが発生しますよ。
ザーッというエフェクターノイズが発生し音が痩せる
シールドが長すぎるのが原因
ザーッっというエフェクターノイズが乗ったり、ギターの音が痩せたり、音質が悪くなる現象はシールドが長すぎるのが原因。
シールドはギターの音の通り道ですが、同時に空気中を漂う電磁波などのノイズを拾うアンテナの役目もしてしまいます。
つまり、シールドを長くするほど、音が出るまでに通過しなければならない距離が長くなり、その間にノイズが乗りやすくなるということです。
又、パッシブタイプ(乾電池を使わない)のエレキギターは、インピーダンスが高いので、シールドを長くするほど、ザーッというノイズが乗ったり、ギターの音痩せや音質劣化を起こしやすくなります。
シールドコードはなるべく短くして対策
とにかく、シールドの長さは必要最小限に留めておくことです。
3m、長くても5mくらいで留めておきましょう。
10mまで伸ばすと、間違いなく悪影響が起こります。
どうしても長く伸ばしたい場合は、アクティブタイプ(乾電池を入れる)のギターに替える。
もしくはストラップにバッファーアンプをガムテープで貼り付けて、それを経由してからシールドをつなぐと改善されます。
バッファーアンプは楽器屋さんではなかなかお目にかかれませんが、自作エフェクター本などには「簡単に作れるエフェクター」としてトランジスタ1個の回路から紹介されています。
製作費も数百円程度から紹介されていますし、ネットでも数多くの情報が掲載されていますから、自作してみるのも良いと思います。
シールドの長さ対策の関連記事
ギターシールドが長くなってしまう場合は!

いっそシールドはワイヤレスにすると長さも気になりません

トラック無線によるエフェクターノイズ
トラック無線ノイズは通信機の違法改造が原因
最近は少なくなりましたが、稀にギターアンプから無線の声が聞こえることがあります。
トラック運転手の中には、無線機を搭載して会話や情報交換をしながら運転している人たちがいます。
その中に受信や発信状態を改善しようとして、違法に出力を大きくしている人がいます。
そのような人が通信しながら近所を通行すると、ギターの音声に無線の声が混入するのです。
無線ノイズはノイズゲートで対策
トラック無線の混入は、歪み系のエフェクターをオフにすれば、かなり小さくなりますが、それでは演奏に影響が出てしまいます。
建物自体の構造が原因なので、プレイヤー側はどうすることもできませんが、ある程度の音量ならノイズゲートで対応することは可能です。
ノイズゲートって何という方はコチラ
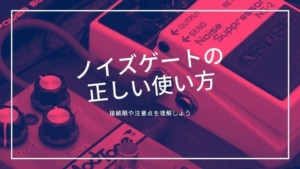
人気ノイズゲートを見たい方はコチラ
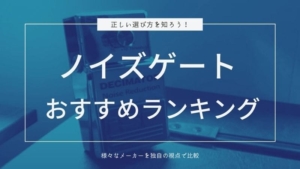
その他のエフェクターノイズの原因と対策
配線の取り回し
エフェクターボードでスイッチャーを使っている人は、パッチコードの取り回しに気を付けてください。
スイッチャーとエフェクターをセンドリターンでつなぐ場合、ループ配線したコードがリング状(円状)に置かれているとノイズが乗りやすくなります。
もし、ループ配線でリングができてしまうと、その輪の面積が大きいほどノイズが乗りやすくなるのです。
リングにならなければ良いのですから、センドリターンの2本の線を束ねておけばこの問題は解決します。
コンプレッサーもノイズが乗りやすい
ディストーションやファズなどは、歪ませるほどノイズが乗ります。
しかし、全く歪み効果がないコンプレッサーも、かかり具合を深くする(SENSを上げる)ほどノイズが増えるのです。
特に、コンプレッサーの場合は、かかっているかどうかが分かりにくいエフェクターなので、かけすぎには注意が必要です。
ノイズが少ないエフェクターを選ぶ
同じ効果が得られるエフェクターでも、ノイズが乗りやすいもの、ノイズが乗りにくいものがあります。
特にノイズの多さに違いが出るのが、ディレイやリバーブなどの空間系エフェクターです。
アナログ式とデジタル式を比較した場合、どうしてもアナログ式の方がノイズが多い傾向にあります。
又、空間系エフェクターは余韻や音の消え方が重視されます。
したがって、エフェクターを繋ぐ順番は、ノイズゲートやノイズリダクションの後になるのが普通です。
そのため、空間系エフェクターはノイズゲートを通らないので、ノイズをカットすることが難しいのです。
逆に歪み系などはノイズゲートの前に繋ぐことが多く、ノイズゲートを通ってくるためノイズを抑えることができます。
ですから、ノイズ対策の面から考えると空間系エフェクターはデジタル式の方がおすすめです。
エフェクターボード内の配置に注意
エフェクターボードは狭い面積に多くのエフェクターを並べるので、それぞれのエフェクター同士が干渉してノイズが乗りやすい環境になっています。
特に真空管式のディストーションやオーバードライブが組み込まれていると、高い電圧を使い発熱し、ノイズが発生しやすくなります。
そのそばに、ブースト系のエフェクターが置かれていると、ちょっとのノイズでも大きくなってしまいます。
ですから、狭いエフェクターボードにたくさんのエフェクターを詰め込みすぎないように、余裕を持ったレイアウトを考えたほうが良いと思います。
扱いやすいエフェクターボードはペダルトレイン。
ビックサイズもありまた配線も下に隠せるため、かなりおすすめです。

宅録は家電に注意
YouTubeや自宅録音など、自室でエレキギターやベースの音を録音する場合は、家電から発生している電磁波にも注意しましょう。
まず、パソコンはノイズの塊です。
また、テレビや照明器具もノイズを発生しています。
特に、掃除機やドライヤーなど、モーターが入っている家電は要注意。
収録中はこれらの家電を使用しないのがベストですが、DTMやDAWなどはパソコン無しでは作業ができません…。
ですから、エフェクターはなるべくパソコンや家電から離して使うなどの工夫が大切です。
むしろ家電によるエフェクターノイズはこれくらいしかありません
あとはフェライトコアのようなノイズフィルターを設置して録音するのがベストかと思います。
フェライトコアはコチラ
使用しないエフェクターは外す
エフェクターボードの中で使用していないエフェクターがあったら、真っ先に外しましょう。
エフェクターを繋げすぎるのはノイズの素です。
仮にすべてのエフェクターをオフにしていたとしても、昔のように、トゥルーバイパスなスイッチでない限りは、完璧なオフ状態ではないのです。
現在のエフェクターは、スイッチングノイズ対策のために、電子スイッチが主流になっています。
したがって、いくらエフェクターをオフにしていると言っても、エフェクターの回路を経由していることに変わりありません。
ですから、エフェクターの繋ぎすぎはエレキギターの原音を変えてしまいますので、エフェクターのかかりが弱くなったり、音痩せの原因にもなってしまうのです。
更に、エフェクターのイン/アウトにシールドを繋ぐ個数が増えるほど、接触不良によるノイズの原因にもなりますので、繋ぎすぎに良いことはひとつもありません。
使用しないエフェクターをエフェクターボードに入れっぱなしにしておくと、持ち運ぶ際にも苦労しますから、今すぐ外すことをおすすめします。
エフェクターノイズの点検と対処方法
最後に、ノイズが乗った時の点検と対処の方法をまとめておきます。
すべてのエフェクター、ループスイッチをオフにします。
この時点でノイズが消えたら、エフェクターに原因があるという事が分かります。
逆に消えなかったら、パッチケーブルやエフェクターのジャックに問題があるということです。
ケーブルやジャックに問題があった場合は、金属磨きと綿棒、ティッシュなどで接点を掃除します。
この場合、ひとつずつ点検してノイズの原因を探していくよりは、すべての箇所を掃除したほうが手っ取り早いです。
又、シールドのプラグ部分もチェックが必要です。
プラグのカバーを回して外し、内部の配線がキチンと繋がっているかも確認しましょう。
ハンダが外れていたり線が切れそうになっている場合は、シールド線を交換するか修理しなければなりません。
上記のSTEP3まで試してみて、まだノイズが乗る場合は、エフェクター本体にノイズの原因があるかもしれません。
エフェクターに問題があった場合は、1台ずつオンにしていき、どのエフェクターがノイズの発生源かを追求します。
ノイズ発生源のエフェクターが見つかったら、エフェクターボードから取り出して、エレキギターとエフェクターを直接に繋いで、アンプから音を出して確認します。
それでもノイズが消えなかったら、パワーサプライを止めて乾電池に替えてみましょう。
乾電池でノイズが消えたら、パワーサプライとの相性が悪いので、パワーサプライを交換します。
又、1台のパワーサプライから数多くのエフェクターへ電源を供給していると、相互に干渉してノイズが乗ることもあります。
他のエフェクターの電源コードを抜いてみるのも、有効な点検方法です。
もし、乾電池でもノイズが乗っていたら、エフェクター本体に問題があるということです。
この場合、エフェクターの故障ならば修理の必要があります。
しかし、エフェクター本来の性能だったとしたら、エフェクター内部に銅箔テープを貼ってシールドし直すなどの改造が必要になるかもしれません。
エフェクターノイズの原因と対策まとめ
上記ではエフェクターからノイズが発生しうる全ての原因及びその対策を解説してきました。
上記の対策をやってみてまだノイズが乗る場合は、
- 故障の可能性があるので修理に出す
- 買い替える
- エフェクター以外に原因がある
この3つの選択肢があります。
ノイズが発生する原因はエフェクターだけではないので、一概に故障とも言い切れないので注意が必要です。
ノイズはギター本体からも、また、アンプからも発生しています。
また、ストラトのようにノイズに悩まされやすい固有体もあります。
以下の記事ではギターのノイズ、アンプのノイズに関して詳しくまとめているのであわせてご覧ください。
ノイズに関する記事
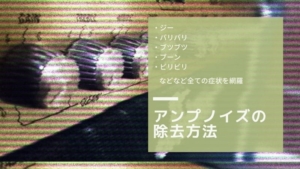


また、ノイズゲートもノイズを排除するポイントになるので、導入していない方は以下の記事を参考にしてください。
ノイズゲートに関する記事
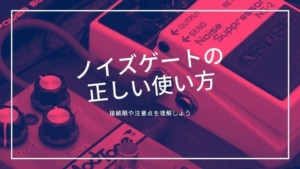
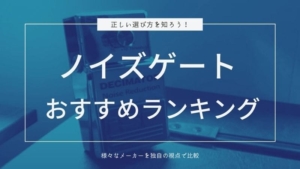


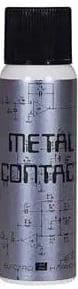


コメント